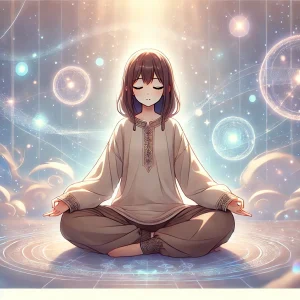Pythonを始めたばかりの頃って、「何から覚えればいいの?」と迷いますよね。
私も最初の1か月は、毎日エラーと格闘していました。
でも、安心してください。
Pythonは“世界一やさしいプログラミング言語”とも言われるほど、初心者に優しい設計になっています。
この30日間で、基本文法をひと通り理解して、簡単なスクリプト(自動処理プログラム)を作れるようになることを目指しましょう。
Pythonの学習を始める前に知っておきたいこと
Pythonの特徴は「読みやすさ」と「シンプルさ」です。
たとえば他の言語では、カッコやセミコロンを多用しますが、Pythonではインデント(字下げ)で構造を表します。
つまり、“きれいに書くことがルール”なんですね。
これは、初心者が「どこでエラーが出ているのか」を見つけやすくするためでもあります。
学習を始める前に準備しておきたいのは以下の3つです。
-
Python公式サイトから最新版をインストール(python.org)
-
エディタ(VSCode など)を使って編集
-
「Hello, World!」を出力して環境確認
この3ステップだけで、もう“Pythonプログラマーの第一歩”を踏み出したことになります。
1. まずは「変数」と「データ型」を理解しよう
変数とは?
変数は、値を入れておく“箱”のようなものです。
Pythonではとてもシンプルに書けます。
name = "Taro"
age = 25
他の言語だと「型」を宣言する必要がありますが、Pythonは自動で判断してくれます。
これが「動的型付け」と呼ばれる特徴です。
主なデータ型
-
文字列(str):「"Hello"」のように文字を扱う
-
整数(int):1, 2, 3 のような数
-
小数(float):3.14 など
-
リスト(list):[1, 2, 3] のように複数のデータをまとめる
まずは、いろんな値を変数に代入して、print()で出力してみましょう。
それだけでもかなり理解が深まります。
2. 条件分岐 if文 でプログラムに“判断”させる
たとえば、「年齢が20歳以上なら大人、それ未満なら子ども」と出力するなら次のように書きます。
age = 18
if age >= 20:
print("大人です")
else:
print("子どもです")
if、elif、elseの3つを使うことで、柔軟な条件分岐が可能になります。
Pythonのインデントは「スペース4つ」が基本ルール。
これを守らないとエラーになります。最初は面倒に感じても、慣れると読みやすくて快適です。
3. 繰り返し処理 for文 と while文
繰り返し(ループ)は、Pythonの学習で最も使う要素のひとつです。
同じ処理を何度も書かなくていいので、効率的にコードを書けます。
for i in range(5):
print(i)
上の例では「0から4まで」順に出力します。
range(5)は0から始まり、5の手前で止まることを覚えておきましょう。
また、while文を使えば「条件を満たすまで繰り返す」ことも可能です。
count = 0
while count < 5:
print(count)
count += 1
4. 関数 def でコードをまとめよう
関数は、「よく使う処理をひとまとめにして、必要なときに呼び出す」ための仕組みです。
def greet(name):
print(f"こんにちは、{name}さん!")
greet("太郎")
defのあとに関数名を書いて、()内に引数を指定します。
関数を作っておくと、プログラムの再利用性がぐっと上がります。
実務でも、自作関数を多く持っている人は仕事が速いです。
初心者のうちから“関数をまとめる癖”をつけておくと、後々の成長が早くなります。
5. リスト・辞書・タプルを使いこなす
Pythonでは「データをまとめる」方法がいくつかあります。
それぞれ使いどころが違うので、例で覚えましょう。
# リスト
fruits = ["りんご", "バナナ", "みかん"]
# 辞書
person = {"name": "Taro", "age": 25}
# タプル
position = (35.6, 139.7)
-
リスト:順番を持ったデータ(編集可能)
-
辞書:キーと値のペアで管理(柔軟)
-
タプル:変更できないデータ(固定情報向け)
最初はリストだけ使えれば十分ですが、辞書を使うと「名前→年齢」みたいなデータ整理がとても楽になります。
6. ファイル操作と入力出力の基本
現実的なプログラムでは、ファイルを読み書きする場面が必ず出てきます。
# ファイルに書き込む
with open("sample.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
f.write("こんにちはPython")
# ファイルを読む
with open("sample.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
text = f.read()
print(text)
with open()構文は「自動で閉じる」安心設計。
初心者でもミスが少なく、安全に使える仕組みです。
7. 30日間のおすすめ学習スケジュール
| 期間 | 内容 |
|---|---|
| 1〜5日目 | Pythonの環境構築とprint練習 |
| 6〜10日目 | 変数・データ型・演算子 |
| 11〜15日目 | if文・for文・while文 |
| 16〜20日目 | 関数とリスト操作 |
| 21〜25日目 | ファイル操作・例外処理 |
| 26〜30日目 | ミニプロジェクト作成(電卓や日記アプリなど) |
このスケジュールをベースに、毎日少しずつ手を動かすのがポイント。
Pythonは「読むより書く」ほうが上達が早い言語です。
たとえば、簡単な日記アプリや家計簿スクリプトを作るだけでも、達成感が得られます。
まとめ(結論・学び)
Pythonを30日でマスターすることは「可能」です。
ただし、“完璧に覚える”よりも“使いながら覚える”ことを意識しましょう。
-
間違えても気にしない
-
printで中身を確認する
-
一つずつ積み上げる
この3つを意識するだけで、初心者から中級者への階段を登れます。
最初の30日間は「基本文法を理解する期間」。
次の30日間は「自分で何かを作る期間」。
その先には、きっと「Pythonで人生を便利にする世界」が待っています。
さあ、今日から一歩を踏み出していきましょう。